「かがくこばなし」では、サイテク部員が身の回りに潜む科学の不思議を紹介します! 今回のテーマは、「黒体輻射」です。 キーワード:色温度、放射温度計、黒体輻射 執筆:T.S.
昼の太陽は白色に見えます。
どうしてでしょう?

実はものはとても熱くなると(目に見える)光を発するようになります。
そしてその光の色は温度によって決まるのです。
太陽の表面温度は6000℃くらい。
これだけ熱くなると白い光をだすようになるんですね。
一方で私たちの体温は36℃くらいなので(目に見える)光をだすことはありません。
他に熱くなって、光っているものはないでしょうか?
たとえば、白熱電球や溶鉱炉の融けた鉄、夜に瞬く星々などがあります。
火もそうですが、火は他のいろんな要素も組み合わさっています。

いろいろなものの温度と色の関係を調べてみるとおもしろいかもしれませんね。
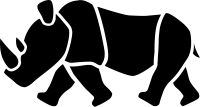 ScienceTechno
ScienceTechno 

